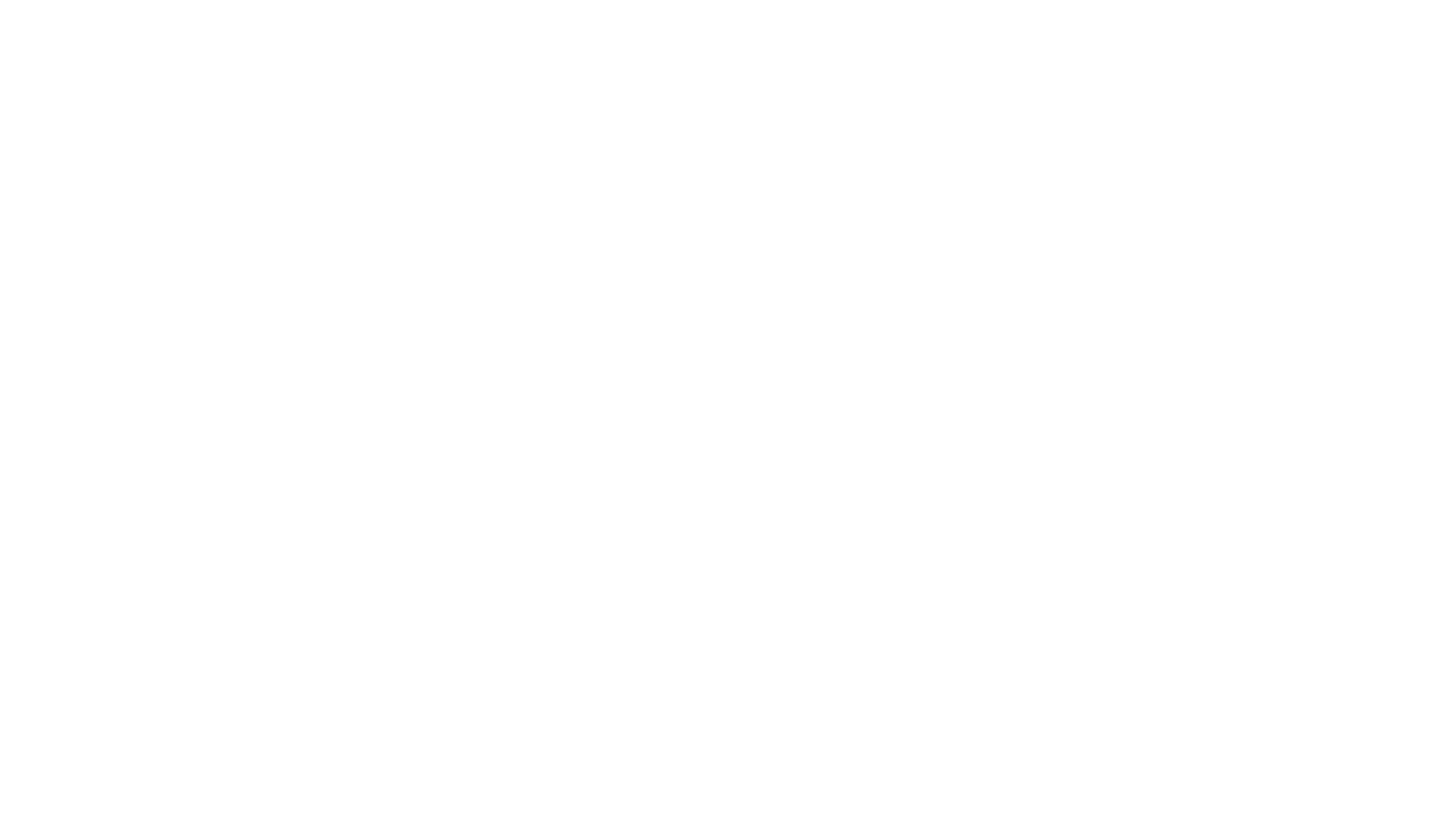『文字が頭に入ってこない…』
『何の話だっけ…』
『ぼーっとしちゃう…』
相手の話や文字を追いかけている時、このような状態になったことはないでしょうか?
このような状況が比較的よくあり、長年の悩みでもありました。
私の場合、いくつかのコツを試行することでだいぶ改善しました。
今日は、そのコツを書いてみたいと思います。
※インプットしたものが垂れ流しのイメージ
(この状態からは脱しましょう)
カラダを動かす
カラダを動かす観点で、2点あげてみたいと思います。
①口に出す=音読する
1つ目は口に出すということ。
つまり、『音読をする』ということです。
これは、対面ではなく、文献の読み込みや読書等の場面を想定いただければと思います。
黙読と音読を比較してみると、音読は『脳が非常に活性化している』といった研究も数多くあり、実感としても間違いないかなと。
音読は単なる読書方法ではなく、記憶力向上、脳の活性化、リラックス効果を同時に得られる優れた学習・健康法であることが分かっている。
- 記憶定着:黙読の1.2〜2.7倍の効果
- 脳の健康:前頭葉の活性化で認知機能向上
- 発達支援:子どもの読解力と集中力を効果的に育成
- 癒し効果:読み聞かせによるストレス軽減
年齢を問わず生涯にわたって認知的健康を支える、科学的に裏付けられた効果的な活動である。
主要参考文献
-
高橋麻衣子「人はなぜ音読をするのか—読み能力の発達における音読の役割—」教育心理学研究, 2013 J-STAGE
-
高橋麻衣子「文理解における黙読と音読の認知過程 注意資源と音韻変換の役割に注目して」教育心理学研究, 2007 J-STAGE
-
BBC Future「The Surprising Power of Reading Aloud」2020 BBC
-
川島隆太ら「Beneficial effects of reading aloud and solving simple arithmetic problems」PLoS One, 2012 PMC
-
森慶子「『絵本の読み聞かせ』の効果の脳科学的分析」ソーシャル・リサーチ, 2015 J-STAGE
-
金沢大学「母親の読み聞かせの影響力 子どもが集中するのに伴い脳内ネットワークが効率化」2021 金沢大学
音読関係で関連書籍を1冊。
声に出して読みたい日本語
例えば、英語学習の世界において、音読は『最高の学習法』との位置づけになっていますし、
他の分野でも音読を活かさない手はないかなと。
ということで、少しでも『頭に入って来ないな…』と思った時には、口に出して再読してみましょう。
声が出せないような場面(例えば電車など)であれば、『ささやき声』や『心の中で呟く』でもOKです。
ここで言いたいのは、『黙読で頭がストップしているなら、違う方法を試そう』ということです。
失敗の本質は『前例踏襲』なので。
上手く行っていない時は、同じことを続けるのではなく方法を変えていきましょう。
②手を動かす=メモをする
2つ目は手を動かすということ。
要するに『メモをする』という話です。
これは対面する相手に積極的に使いたいものです。
メモの仕方は色々ありますが、まずはメモをすること自体が大切かなと。
興味関心を自分にも相手にも示すことになりますので。
メモの内容は自由です。
- 相手が話してる内容
- 自分が大事だと思ったポイント
- 行動につながると思った点
- 質問したいこと
など、手を動かしていくと、相手の話がすっと入ってくる感覚になります。
私は一時期メモを全く取らない時期があったのですが、これは今でも悔やまれます。
(会社員時代の3年目くらいだった記憶)
これは良くないと思い、メモを取る習慣を取り戻してからは今まで継続しています。
○○するつもりで聞く
次は、持っておきたい『心構え』の話です。
①『誰かに説明するつもり』で聴く
1つ目は『誰かに説明するつもりで聴く』ということです。
言い換えると『アウトプットを前提としてインプットする』ということで、大切なポイントです。
誰かに説明するのであれば、相手の話を受け止め、内容を咀嚼する必要が出てきます。
この内容の消化するプロセスが良いのです。
相手に説明をするつもりで聞くことで、自分の理解も深まります。
②『相手に質問する』つもりで聴く
2つ目は『相手に質問するつもりで聴く』ということです。
1つ目よりはこちらの方がハードルが少し下がるかなと。
『相手に必ず質問する』という点を自分で課すことで、話を聴く『集中力』が高まります。
漫然と聞いていては質問は出てこないので、これも有効な方法です。
『なかなか質問が考えられない…』
『質問が苦手だ…』
という方も心配ありません。
そんな時は『5W1H』の中で1つのポイントに絞ってみましょう。
例えば、
- 『なぜそう考えたのか?』『なぜそう思ったのか?』『なぜそうするのか?』といった形でWhyに絞る。
- 『どう行動したのか?』『どう行動をしていけばいいのか?』『どのように対処したのか?』といったHow。
他の疑問詞も同様で、この切り口で考えれば、質問は無限に出てくるかなと。
以上2点挙げましたが、共通点は、『行動に繋げる前提で、理解をしていく』いうことです。
分かっただけで満足せず、行動して満足する。
この価値観を持ちたいと、私は考えています。
なお、実際に誰かに説明することや、相手に質問するか否かは問いません。
『するつもりで聴く』という『アウトプット前提の構え』が理解を深めます。
『自分の言葉』で整理する
ここまでの話は、聞いている場面、読んでいる場面といった『その場面にいること』を前提として書きました。
最後に事後の話に触れたいと思います。
事後的には『自分の言葉で整理』するのがおすすめです。
コツは2W1H。
つまり『3つの問い(What・Why・How)』を立てて整理することです。

読書が終わった後や人の話を聞いた後に、例えば以下のような問いを立てて、その答えを書いていきます。
- 何が響いたか?(What?)
- それはなぜか?(Why?)
- 今後どう生かしていくか?(How?)
私の記事も2W1Hでの切り口が多いので、参考にしていただければと思います。



以上、何か参考になれば嬉しいです。
では、また次回。
編集後記
◇日記
早朝ラン&ブログ執筆。
日中は会計士業の打ち合わせを中心に。
(MTGが多い1日でした。。)
仕事が終わった直後に三男と2人で水遊び。
1時間近くベランダで遊んでいました。
◇ブログネタ経緯
今朝の早朝ランで最近読書で音読していたことと繋がりネタに。
◇1日1新
THE NORTH FACE ビッグショット(リュック)
◇今日の一冊
新・貧乏はお金持ち(続き)